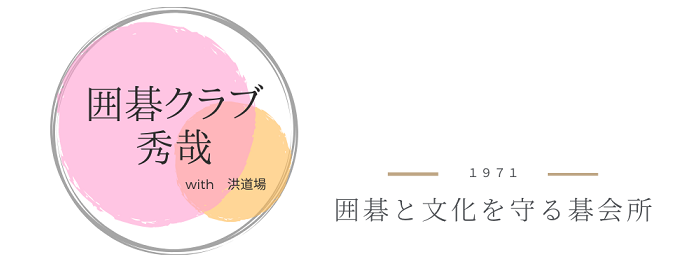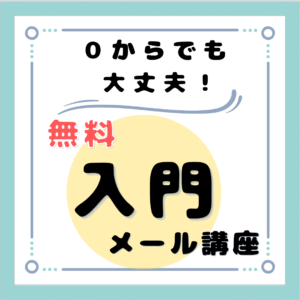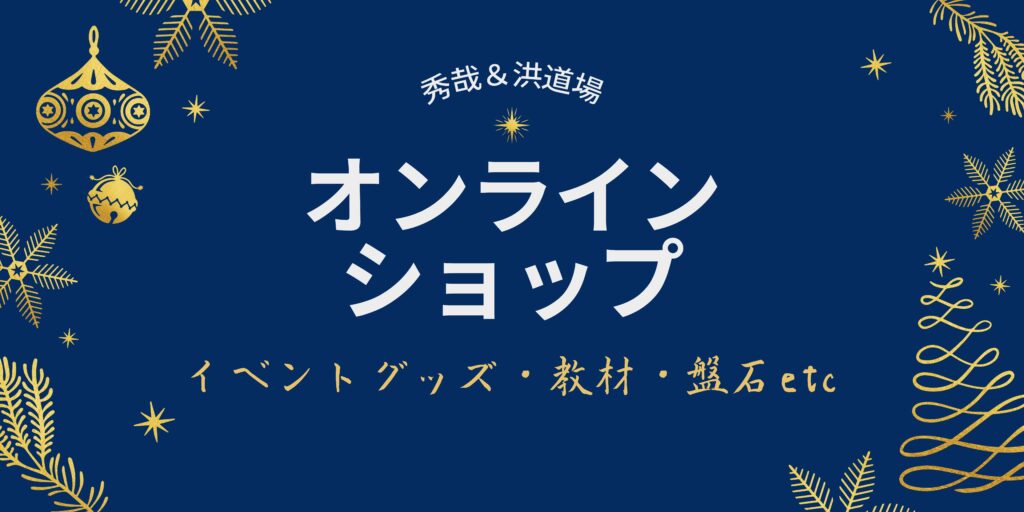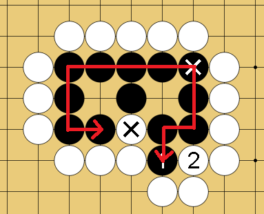
今回は「欠け眼(かけめ)」というものについて学んでいきましょう。
欠け眼は、「眼のようで眼ではない」という紛らわしいものですが、囲碁を打っていく中でとても大事な概念です。
考え方をゆっくり見ていきましょう。
「欠け眼」とは?
欠け眼(かけめ)とは、「石のつながりが欠けた眼」のことです。
どういうことか解説していきますね。
「眼」の仕組み
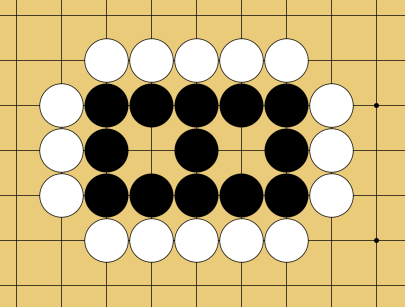
まずはこの図をご覧ください。
この黒は、白に囲まれていますが、
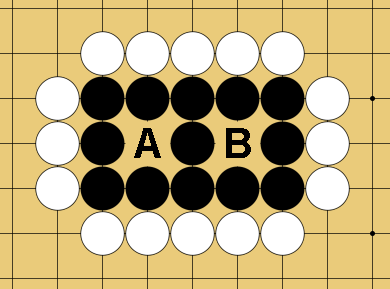
AとBに眼があって、生きています。(取られません。)
仕組みとしては、
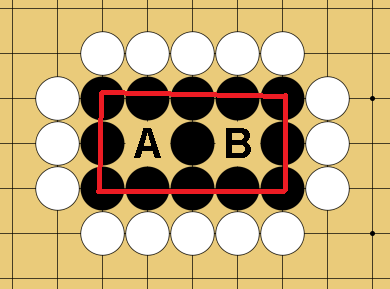
このように縦横の線で、石がちゃんとつながっているから、黒がアタリにされないのです。
ということなので、
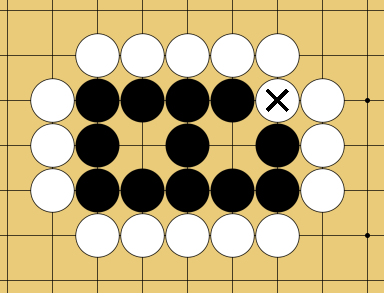
仮に、白×のように一ヵ所が白になったとしても、
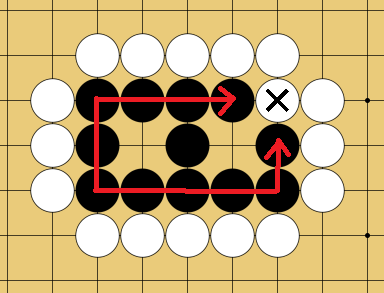
こういう風に線で石がつながっているので、黒はアタリになりません。
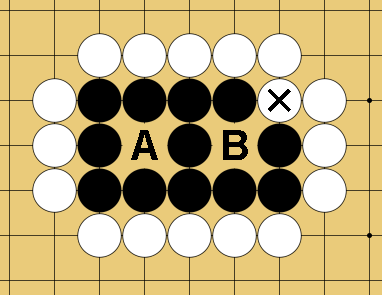
AとBは両方ともちゃんとした「眼」で、黒は生きているのです。
「欠け眼」の仕組み
では、欠け眼の図を見ていきましょう。
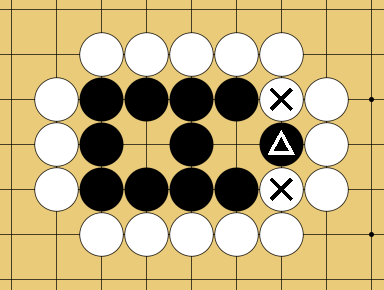
こうなると「欠け眼」になります。
白×が増えたことによって、黒△がアタリになっていますね。
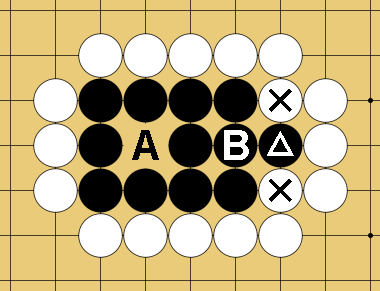
黒Bとつなぐ必要が出てきて、眼が石で埋まってしまいます。
こういう状況が「欠け眼」です。
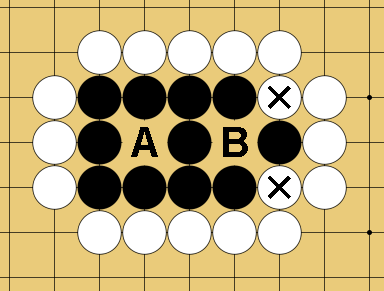
白×がいることで、Bの場所が眼にはならないのです。(Bが欠け眼)
この図の場合は、黒Aの一眼しかできず、黒が全部取られてしまうのですね。
アタリになっていなくても欠け眼
ここが欠け眼の話で難しいところなのですが、
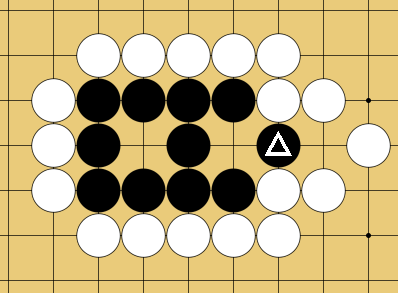
このように、黒△がアタリでなくても
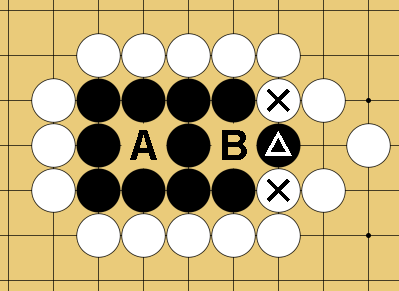
白×につながりをジャマされていると、Bの場所は欠け眼になります。
Aにしか眼がなく、この黒一団は「死に石」になるのです。
黒が助からないことの証明としては、
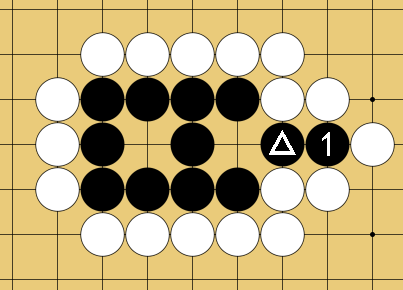
黒が1と抵抗したとしても、黒は結局アタリになってしまいますね。
助けるために石で埋めなければならず、眼にならないのです。
OKでしょうか。
欠け眼の例
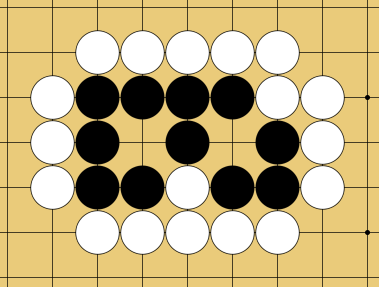
この状況も「欠け眼」です。
どれが欠け眼なのかというと…
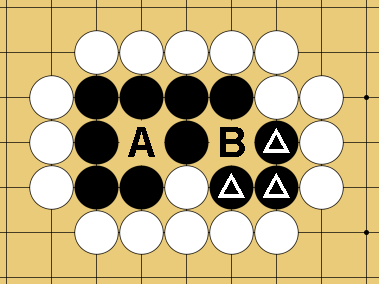
Bの場所です。
よく見ると、黒△がアタリになっていますね。
仕組みとしては、
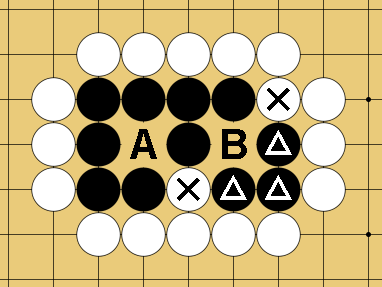
白×によって、黒△が切り離されてしまっているから「欠け眼」になるのです。
白×さえいれば、
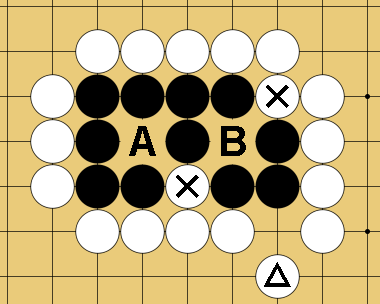
白△がこのように離れていても、
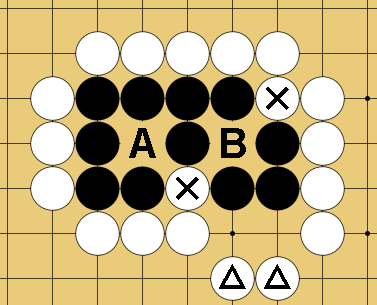
このようになっていても、Bの場所は欠け眼なのです。
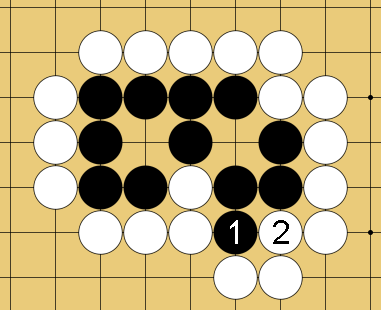
たとえば黒が、黒1などと抵抗をしても、白2と打たれると黒四子がアタリになってしまいますね。
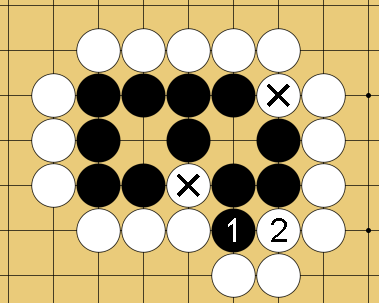
白×がいる限り、黒がアタリになることを避けられないのです。
反対に、
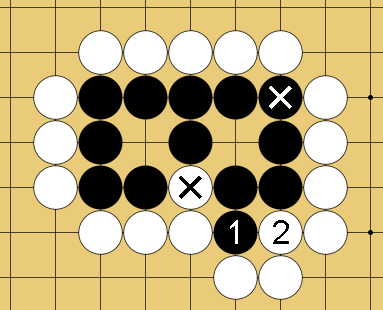
×のどちらかが黒石ならば、この黒はアタリされませんので「二眼」を持って生きている石ということになります。
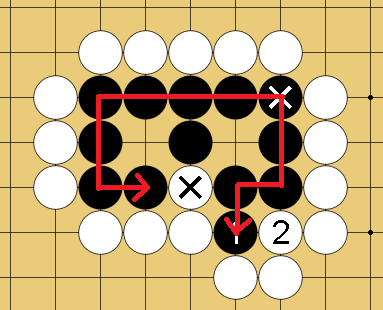
こんな風に縦横の線で、石同士がつながっているということが大事なのでした。
ややこしいところですが、大丈夫そうでしょうか。
まとめ
欠け眼とは、石のつながりが欠けた眼のことで、石の「生き死に」の時に眼としてカウントされません。
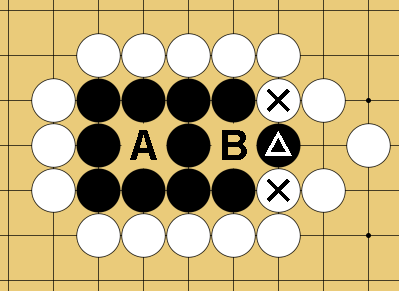
白×によって、Bの場所が欠け眼になっているのでしたね。
反対に、
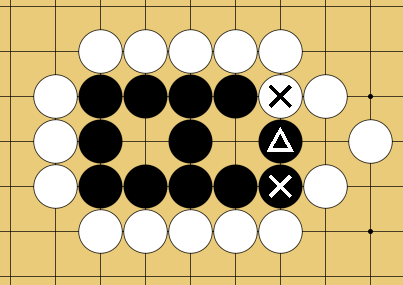
×の場所が黒石になるだけで、
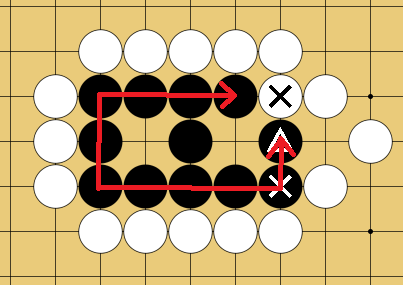
このように石がつながって「眼」になります。
どうでしょうか。
死活の時以外でも、「石がどこまでつながっているのか」を見ることは大切です。
是非、対局のときに意識してみて下さいね。
では、最後まで読んで下さりどうもありがとうございました。
次回もどうぞよろしくお願いします!
※続けて次の記事も見たい方はこちら:
【秀哉の囲碁入門⑲】死活について(5)「中手」とは?